更新日:2025年3月6日
ここから本文です。
法人課税の臨時特例措置に関する報告
このページでは、神奈川県地方税制等研究会「法人課税の臨時特例措置に関する報告(平成13年1月)」を掲載しています。
法人課税の臨時特例措置に関する報告
まえがき
当研究会は、平成12年5月25日、県財政の現状を踏まえた、神奈川らしい税制の基本的な方向性を整理し、外形標準課税問題に対する考え方や、県独自の税収確保策としての超過課税に関する事項について、岡崎知事に中間報告したところである。
とりわけ、都道府県の基幹税目である法人事業税については、課税の独立性を高め、地方分権の時代にふさわしい応益的な地方税体系を構築する上で、外形標準課税の導入は大きな意義を有するものとしたところである。
さらに、法人事業税に外形標準課税が早期に導入される見通しが立たない場合に、法定外普通税・目的税又は地方税法第72条の19の活用により、県独自の措置として、繰越控除制度を遮断するための方策を検討していくことが必要と指摘したところである。
その後、平成12年7月に政府税制調査会から、薄く広く負担を求める外形標準課税について、景気の状況等を踏まえつつ、早期に導入することが必要との中期答申が出され、また、その答申を受け、先般、自治省から具体的な外形標準課税案が示されたところである。
しかしながら、平成13年度税制改正では、外形標準課税の導入が見送られ、早期導入が困難になったので、法律上認められた課税自主権を有効に活用し、神奈川県の危機的な財政状況に起因する県民生活へのマイナス影響を、少しでも縮小する必要があるとの観点に立って、早急に法定外普通税として「臨時特例企業税」を導入することが適当であるとの結論を得たので、ここに取り急ぎ報告するものである。
平成13年1月
神奈川県地方税制等研究会
座長 神野 直彦
1 神奈川らしい税制の構築に向けての基本的方向性
地方分権一括法の施行により、ようやく地方分権型社会の構築に向けて扉が開けられたところであるが、その財政的基盤となるべく、国庫補助金や地方交付税といった移転財源のあり方を含めた国から地方への税財源の移譲については、中期的な課題として先送りされており、こうした課題の解決なしには地方分権も十分な展開をなし得ないところである。
一方、少子高齢時代の到来を迎えるなど、今日、地方自治体の住民ニーズは多岐多様であり、こうした財政需要に対応できる確固たる財政基盤を確立しておくことが、地域住民が求める行政対応を迅速に行う上で不可欠である。
神奈川県では、福祉、医療、教育、環境といった、県民生活に関わる基本的・恒常的なニーズに対応しなければならないとともに、全国平均を上回るスピードで少子・高齢化が進展し、総合的な福祉政策への重点的な取組が求められている。さらに、人口の集中や産業の集積が著しく、道路整備や環境対策などについて、大都市圏特有の財政需要が生じている。
こうした中、今日の神奈川県の財政状況は危機的な状況にあり、その原因は、長期に及ぶ景気低迷により、県税収入が大幅に減少している一方で、義務的経費が増加を続け、歳出入ギャップが拡大していることにある。特に、県税収入の落込みの要因は、かっては県税収入の5割を占めた主力の法人税収が、ピーク時に比べ半減するなど、大幅に落ち込んだことにある(平成元年度5,221億円→平成11年度2,185億円)。
このように、税収が大幅に落ち込んだとしても、地域の法人・個人が活動・生活していくために、行政サービスをその落込みに合わせて減少させることができないことは言うまでもないことである。
したがって、県の提供するサービスの中心が、法人、個人にとって欠くことができない産業基盤や生活基盤の整備である以上、応益原則の観点から、景気に左右されない税制を組み込み、安定した財政基盤を構築しておくことが重要である。
こうしたことを踏まえ、当研究会が、先に報告した「地方税財政制度のあり方に関する中間報告書」(以下「中間報告書」という。)では、地方分権型社会への動きや県財政への現状を踏まえ、神奈川らしい税制の基本的方向として、
(1) 神奈川らしい生活環境や地域経済の振興を重視した税制
(2) 神奈川という大都市圏特有の需要を賄うのにふさわしい税制
(3) 財政危機に対応できる強固な税制
(4) 景気に左右されない安定性を兼ね備えた税制
を構築するという視点が必要であることを指摘したところである。
2 法人課税に対する臨時特例措置の検討
(1) 外形標準課税の導入の必要性
神奈川が財政危機に陥った直接的な原因には、バブル経済崩壊後の長期にわたる景気低迷を背景とした法人税収の落込みがあった。神奈川のように、大都市圏に位置し、かつ、産業が集積し、企業活動が活発な地域にあっては、大都市圏特有の財政需要が生じているため、その財政需要を賄うため、応益的な観点から、企業活動を的確に反映する税制を講じる必要がある。
また、都道府県は、産業振興対策、社会基盤整備といった法人に直接の便益をもたらす施策はもとより、教育、環境対策、治安など広範な行政サービスを地域で活動している法人に提供しており、法人は、行政サービスという一種の生産要素の提供を受けながら事業活動を営んでいる。法人事業税は、まさにこうした生産要素の一つである行政サービスの対価として応益的な性格を持った税として位置づけられる。
しかしながら、現行の課税方式の下では、所得の多寡によって税負担が決定されることから、行政サービスとの受益関係が税負担に的確に反映されていない。加えて、現在、全法人の約7割を占める欠損法人は法人事業税を負担していないため、結果的に、都道府県の最大の基幹税目である法人事業税は、一部の利益法人によってのみ支えられているのが実態である。
中間報告書においては、こうした「応益性・公平性の確保」の観点に加え、法人事業税における「独立主義の確立」、「安定性の確保」、さらに、「経済構造改革と地域の活性化」の4つの観点から、外形標準課税の導入の必要性を整理したところであるが、法人事業税に外形標準課税を導入することは、企業が受ける行政サービスに対する負担を、企業が公平に負担する仕組みとして、また、神奈川らしい税制を構築する上で、重要かつ緊急な課題である。
(2) 法人課税の臨時特例措置の創設
中間報告書において、法人事業税の外形標準課税については、全国的な制度として早期に設けられることが望ましいと提言したところである。自治省など国においても、その早期導入を目指して、努力が続けられてきたが、先般、自治省は、外形標準課税の具体的な案を取りまとめ公表したところである。その案によると、法人の事業活動の規模を表す「事業規模額」を課税標準として採用するとともに、中小法人に配慮した内容になっており、大筋では、当研究会の中間報告の趣旨に沿った内容になっており、地方団体としても、その早期実現に向けて、支援すべきと考える。
そうした中で、神奈川県の危機的な財政状況を見ると、国の制度改正をただ待つことなく、可能な限り課税自主権を活用して、安定的な税制を構築しつつ、財源不足を解消していく努力をすべきと考える
したがって、国において検討されている法人事業税の外形標準課税について、早期導入がされない場合は、課税自主権を活用して、臨時的、かつ特例的な措置として、現行の法人事業税を中心とした都道府県の法人税制を、公平性及び安定性の観点から補完する制度を早急に構築するよう提言したい。
3 臨時特例企業税の創設
(1) 法定外税の活用
中間報告において、外形標準課税が早期に導入される見通しが立たない場合には、現下の厳しい財政状況を踏まえ、臨時的・時限的な対応として、法人事業税について欠損金の繰越控除制度の適用を遮断する措置を講ずることが適当であるとし、この制度改正が実現されない場合には、法定外普通税・目的税の導入又は地方税法(以下「法」という。)第72条の19の活用により、県独自の措置として、繰越制度を遮断するための方策を検討していくことが必要であるとしたところである。
ここでは、外形標準課税の早期導入が難しい場合、地方独自にどのような措置がとれるかについて、当研究会の論議の結果を取りまとめることとする。
なお、この措置を法定外税で講ずるか又は法第72条の19の活用で行うかがまず問題になるが、法第72条の19の規定は、法人事業税において現在、所得を課税標準としている事業について、「事業の情況」に応じて、所得によらないで、資本金額、売上金額等の外形標準課税を用いることができるとしているが、これは、特定の業種について適用が予測されている規定であり、すべての業種を対象とするならばこの規定の意味がないと解されるところ、我々が意図している「繰越欠損金控除」の遮断については、所得を課税対象とするすべての法人に共通することであることから、同条の活用は適当でないと考えられる。そこで法定外税の活用を前提として、制度の構築を考えていくことにする。
(2) 基本的考え方
繰越欠損金の遮断を法定外税で措置しようとするとき、次の論点について整理しなければならない。
(1) 繰越欠損金を遮断する効果のある税制を構築することの是非
(2) 新たな法定外税の課税標準を何にするのか。
(3) 法定外税の法律上の要件への適合
以下、この論点についての考え方を整理する。
ア 繰越欠損金の遮断の考え方
法人税法上、課税標準となる「各事業年度の所得の金額」は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされている(法人税法第21条、第22条第1項)。そして、過去5年間に生じた欠損金額がある場合、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされている(同法第57条第1項)。このように、法人税法上、損金に算入することとしているのは、企業が長期にわたり継続的に活動することを前提としていることから、「所得」の概念には、繰越欠損金を差し引いたものという意味を含んでいると考えられる。
しかしながら、その損金とすべき欠損金を何年間認めるかについては、政策上の判断にゆだねられているというべきであり、また、臨時的にその適用を一部又は全部遮断することは、我が国においても過去に事例があることに加え、外国でも事例が見受けられる。
また、繰越欠損金についても、その性格は、2種類あると言える。すなわち一つは、通常の事業活動から生じた欠損金であり、もう一つは、本来の事業活動から離れて行った土地や株式等の投機活動により生じた欠損金である。この場合、損金として、必ず認めなければならないのは、前者の通常の活動から生じた繰越欠損金であって、後者の投機活動から生じた繰越欠損金は、必ずしも認める必然性はない。
したがって、「所得」を課税標準とする税において、繰越欠損金のすべてを、恒久的に認めない制度を構築することは、課税理論上、疑問視せざるを得ないが、臨時的・時限的にその全部を認めなかったり、また、投機活動から生じた欠損金の繰越を認めないという考え方に立って、欠損金の一定割合の控除を認めないとすることは、税政策上、行い得ると考えられる。
イ 新たな法定外税の課税標準について
そこで繰越欠損金の遮断を行いうる仕組みを持つ新税を考えると、まず、その課税標準として、「当該事業年度において損金に算入した繰越欠損金の額」が考えられるが、このように企業会計上の一定の項目に対して税をかけるという方法も一つの手法としてはあり得る。
しかしながら、このように課税標準が繰越欠損金そのものに連動することは、あたかも欠損金に課税するようで、課税理論上、説明しがたい面がある。そこで、繰越欠損金の控除をした場合は、必ず、当該事業年度において、必ず繰越欠損金に相当する利益が生じていることから、その利益に対して課税するという考え方で課税標準を設定すれば、こうした問題は解消される。
また、臨時的な措置であれば、繰越欠損金のすべてを停止することがあり得ることを前提としつつ、バブル経済以降において、欠損金のかなりの部分が投機的な損失であったことを踏まえて、すべての繰越欠損金の控除を認めないとするのではなく、その一定割合に限って控除を認めない制度として構築することが、繰越控除制度の本質に矛盾しない制度構築として考えられる。その場合の一定割合は、外国の制度等を勘案すると、概ね30%程度までが妥当な範囲と考えられる。
ウ 法定外税の法律上の要件への適合
法定外税を創設する場合、それが法定外普通税であれ、目的税であれ、総務大臣の同意が必要となる。その場合の同意することができない要件として、次の要件が挙げられている。
(1) 国又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
(2) 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
(3) 国の経済政策に照らして適当でないこと
このうち(2)については、流通課税ではないので特に問題は生じないと考えられる。また、(3)については、国の経済政策は、その時々の国民経済の状況において変わるものであり、その内容も流動的であることから、著しく不適応と判断されない限りは、基本的には問題にならないと考える。なお、(1)については、制度の構築の仕方によっては、問題がなしとは言えない場合も考えられるので、これについては、具体的な制度の検討の中で触れることとする。
(3) 臨時特例企業税の具体的内容について
ア 課税の趣旨及び根拠
法人事業税は、行政サービスに対する応益原則の考え方に立って、すべての法人が応分の税負担をすべきであるが、企業活動の結果、当期利益がある法人であっても、欠損金の繰越控除制度の適用により、当期利益に見合った税負担が生じないこととなっているため、外形標準課税が導入されるまでの間の臨時的、特例的な措置として、一定規模以上の法人に、相応の負担を求める法定外普通税として創設することが適当と考える。
イ 課税標準
課税標準については、(2)ア及びイの検討結果を踏まえると、欠損金の繰越控除額の一定割合(30%×法人事業税の分割基準の相当する割合)に相当する当期利益が課税標準となる案が考えられるが、これを定義すると、「各事業年度の法人事業税の課税標準である所得に、当該所得の計算に当たって損金に算入した繰越欠損金に相当する額を加算した額に一定の割合(30%×法人事業税の分割基準の相当する割合)を乗じた額。ただし、当該額が、繰越欠損金に相当する額の一定の割合を上回る場合は、当該繰越欠損金に相当する額を上限とする。」となる。
このただし書は、当期利益が生じた場合で、欠損金の繰越控除額を損金に算入しても、さらに法人事業税の課税所得が生じるとき、このような限度額を設定することにより、欠損金の繰越控除額相当分のみを課税対象となるよう、仕組むために設けるものであり、これにより、法人事業税との二重課税を避けることができるものである。
なお、この場合の一定割合に含まれる30%は、臨時的に繰越欠損金の全部又はその一部を適用しないことが税政策上とることが可能であること、繰越欠損金には投機的損失が含まれており、その部分については、欠損金の繰越を否定しうること等を、総合的に勘案して繰越欠損金のうち課税対象とする部分の割合を設定したものである。
しかしながら、こうした率を課税標準の中に組み込むことは、分かりやすい税制度とする観点からすると、かならずしも適当とは言えないことから、当研究会においては、この率は、税率設定の中で考慮することが、適当であるとの結論を得たところである。
したがって、課税標準については、「各事業年度の法人事業税の課税標準である所得に、当該所得の計算に当たって損金に算入した繰越欠損金に相当する額を加算した額に一定の割合(法人事業税の分割基準の相当する割合)を乗じた額。ただし、当該額が、繰越欠損金に相当する額を上回る場合は、当該繰越欠損に相当する額を上限とする。」ことが適当である。
なお、この場合、法定外税の総務大臣の同意要件である「国又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること」への関連をどのように考えるべきかについては、まず形式的にみても、法人税や法人事業税の課税標準である「所得」と、新税の「法人事業税の課税標準である所得に損金に算入した繰越欠損金に相当する額を加算した額」は、概念上、明らかに異なるものであり、また、実質でみても、新税の課税標準は、当該事業年度において控除した繰越欠損金額と同額になることから、二重課税の問題は生ぜず、法人税や法人事業税の課税標準との重複の問題は生じ得ないと考えられる。
ウ 納税義務者
納税義務者については、「各事業年度の法人事業税の課税標準である所得の計算に当たって繰越欠損金に相当する額を損金に算入した法人で、資本金額又は出資金額が5億円以上のもの(公共法人及び公益法人等並びに清算法人を除く。)」とすることが適当と考える。
資本金額又は出資金額が5億円以上の法人を納税義務者とするのは、
(1) 繰越欠損金の適用法人は、赤字から黒字に転換したばかりの法人であるため、その担税力に配慮し、資本金額等については、一般的な中小法人の基準よりも高く設定する必要があること、
(2) 対象とする法人は相当程度体力があり、社会的責任を求められる大会社に限定することが適当であること、
(3) その大会社の基準としては、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律において、会計監査人の監査を強制するなど、一般の会社よりも厳格な監査に服させるとともに、その経営内容の開示を強化する大会社について、資本金額5億円以上としていること
等を踏まえたものである。
また、企業活動に対する行政サービスの対価として応分の負担を求めるという課税の趣旨を踏まえ、営利目的の企業活動を目的としない公共法人及び公益法人等並びに企業活動を終了した清算法人については納税義務者から除外すべきである。
エ 税率
税率については、先に述べたとおり、繰越欠損金の一部について控除を認めないという考え方を、課税標準で反映せずに、税率で反映するという考え方に立って、その一定割合分30%と、法人事業税の税率水準が10%程度であること踏まえ、両者を掛け合わせた3%(特別法人は2%)とすることが適当と考える。
オ 名称
名称については、以上述べてきたとおり、新税は、企業活動に着目し、法人課税の臨時的、特例的な措置として、一定の大会社を納税義務者とする税として、創設しようとすることから、その名称は「臨時特例企業税」とすることが適当である。
カ 賦課徴収の方法
臨時特例企業税は、法人事業税を補完する性格を有することから、法人事業税の賦課徴収制度を参考にして、次のような賦課徴収の方法を採用すべきである。
(1) 申告納付の方法による。ただし、確定申告及び修正申告のみとし中間申告は義務付けない。
(2) 欠損金の繰越控除を適用した事業年度分のみを対象として申告義務を課す。
(3) 申告期限(延長期限を含む。)は、法人事業税と同じとする。
(4) 申告書の添付書類として、法人税申告書別表4(所得の金額の計算に関する明細書)の写しの提出を義務づける。
以上の内容について、まとめると次の別表1のとおりとなり、また、その仕組みを図表化すると別表2のとおりとなる。
別表1
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 課税の根拠 | 地方税法第4条第3項の規定に基づく法定外普通税 |
| 課税の趣旨 | 外形標準課税が導入されるまでの間の臨時特例措置として、県の行政サービスを享受し、かつ当該事業年度において利益が発生していながら、欠損金の繰越控除により相応の税負担をしていない法人に対し、担税力に見合う一定の税負担を求める。 |
| 名称 | 臨時特例企業税 |
| 納税義務者 | 各事業年度の法人事業税の課税標準である所得の計算に当たって繰越欠損金(災害による繰越欠損金を除く。以下同じ。)に相当する額を損金に算入した法人で、資本金額又は出資金額の金額が5億円以上のもの(公共法人及び公益法人等並びに清算法人を除く。) |
| 課税標準 | 各事業年度の法人事業税の課税標準である所得に、当該所得の計算に当たって損金に算入した繰越欠損金に相当する額を加算した額(当該額が繰越欠損金に相当する額を上回る場合は、繰越欠損金に相当する額を上限とする。)に一定の割合<法人事業税の分割基準に相当する割合>を乗じた額 |
| 税率 | 3%(特別法人は2%) |
| 賦課徴収の方法 | (1) 申告納付の方法による。ただし、確定申告及び修正申告のみとする。 (2) 欠損金の繰越控除を適用した事業年度分のみを対象として申告義務を課する。 (3) 申告期限(延長期限を含む。)は法人事業税と同じとする。 (4) 申告書の添付資料として、法人税申告書別表4(所得の金額の計算に関する明細書)の写しの提出を義務づける。 |
別表2
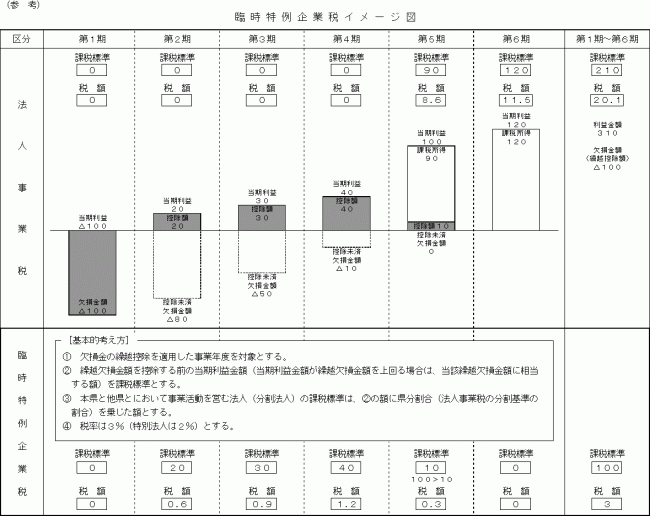
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。